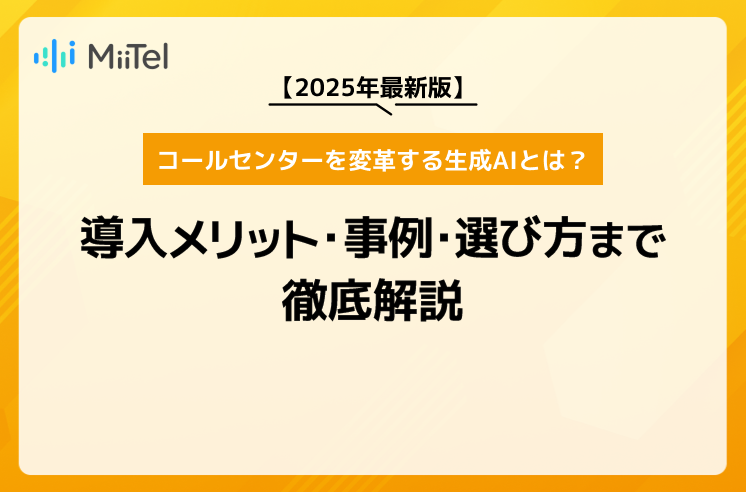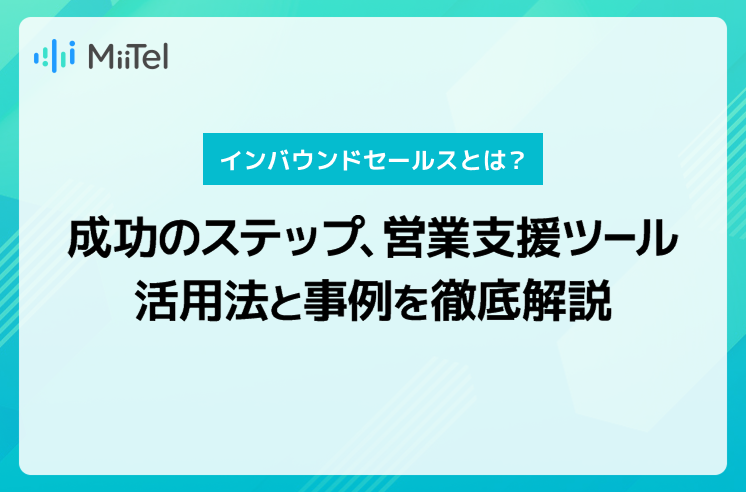コールセンターのAHT(平均処理時間)とは?意味や計算方法、7つの短縮方法を解説
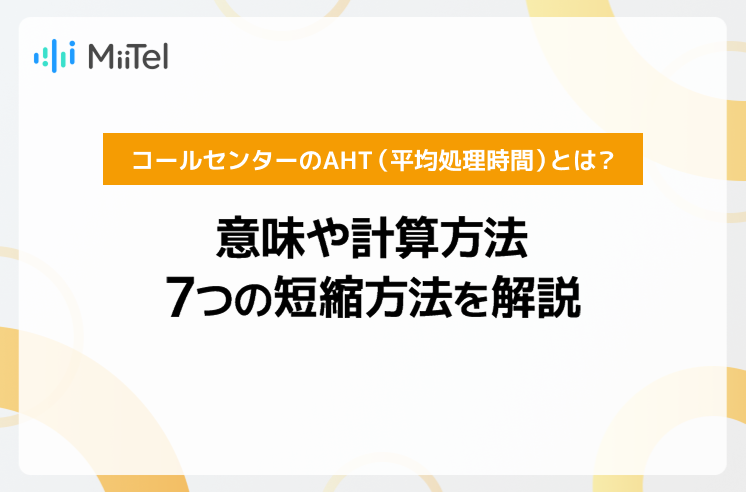
インサイドセールス・電話営業の業績向上なら電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」
インサイドセールス・電話営業の業績向上なら
電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」
目次
AHT(Average Handling Time:平均処理時間)は、顧客からの問い合わせ1件あたりに費やす時間の平均値です。この指標を適切に管理・改善することは、コールセンターの生産性向上と顧客満足度の維持に直結します。
AHTの改善は、単なる時間短縮ではなく、顧客満足度との両立が重要です。そのためには、原因分析から具体的な改善策の立案、そして適切な目標設定まで体系的なアプローチが求められます。
この記事では、AHTの基本的な知識から計算方法、顧客満足度を損なわずにAHTを改善する具体的な手法まで、専門的な視点からわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
- AHTの意味と重要性
- AHTの具体的な計算方法と業界平均
- AHTが長くなる5つの主な原因
- 明日から実践できるAHTの具体的な改善策
- AHT改善に取り組む上での注意点
AHT(平均処理時間)とは、コールセンターの効率性を評価する指標
この章の要約!
AHTとは、1コールあたりの平均処理時間を示し、コールセンターの「効率性」と「応対品質」を測る重要な指標です。この数値を正しく理解し管理することが、センター運営改善の第一歩となります。
AHTは、コールセンターを運営するうえで欠かせない指標です。その定義を正しく理解し、ATTやACWといった関連指標との違いを把握することで、自社の課題がどこにあるのかを明確に分析できます。
AHTの意味
AHTは「Average Handling Time」の略語で、日本語では「平均処理時間」と訳されます。顧客からの問い合わせ1件に対応するために、オペレーターが費やした時間の平均値のことです。
AHTは主に効率を測る指標であり、品質は顧客満足度や品質評価指標と組み合わせて評価します。
コールセンターの生産性や応対品質、さらには必要な人員数を算出するための重要なKPI(重要業績評価指標)として広く活用されています。
AHTとATT・ACWなどの関連指標の関係
AHTは複数の業務時間の合計で構成されます。特に混同されやすいのが、AHTを構成するATT(平均通話時間)やACW(平均後処理時間)という関連指標です。
以下に、AHTと関連指標の関係性をまとめました。
| 指標名 | 内容 |
|---|---|
| AHT(平均処理時間) | ATT、ACW、保留時間の合計。1コール対応の総時間 |
| ATT(平均通話時間) | 顧客とオペレーターが実際に会話している時間の平均 |
| ACW(平均後処理時間) | 通話終了後、応対内容の履歴入力やフォローアップなどを行う作業時間の平均 |
| 保留時間 | オペレーターがSVへの確認や情報検索のために顧客を待たせている時間の平均 |
これらの関係性を正確に理解することが、AHT改善の第一歩です。
AHTの計算方法と業界別の平均時間
この章の要約!
AHTは「(総通話時間+総後処理時間+総保留時間)÷ 総処理コール数」で算出できます。業界や業務内容で平均は異なりますが、一般的な目標は約6分(360秒)と言われています。
自社のAHTが適正かどうか判断するには、まず正確な計算方法を知る必要があります。その上で、業界の平均的な数値と比較することで、自社のコールセンターの立ち位置を客観的に把握できるのです。
AHTは、オペレーターが顧客対応に費やした全ての時間を合計し、対応したコール数で割ることで算出できます。
計算式は以下の通りです。この式を用いて、自社の現状を数値で正確に把握しましょう。
AHT = (総通話時間 + 総後処理時間 + 総保留時間) ÷ 総処理コール数
なお、AHTの目安として「6〜7分」という数値を耳にすることもあるかもしれません。
株式会社リックテレコム発行「コールセンター白書」によれば、ATT(平均通話時間)の平均値は6.75分、ACW(平均後処理時間)の平均値は4.8分です。
このデータを基に、「AHT = (総通話時間 + 総後処理時間 + 総保留時間) ÷ 総処理コール数」の計算式がどのように使われるか、具体的な例を挙げてみます。
▼あるコールセンターの1日の実績データ(例)
- 総処理コール数: 200件
- 総通話時間: 1350分 (← 6.75分 × 200件)
- 総後処理時間: 960分 (← 4.8分 × 200件)
- 総保留時間: 100分 (← 1コールあたり平均30秒と仮定)
これらの数値を、AHTの公式に当てはめて計算します。
- AHT = (1350分 + 960分 + 100分) ÷ 200件
- AHT = 2410分 ÷ 200件
- AHT = 12.05分
このコールセンターのある日のAHTは、「12.05分(約12分3秒)」と算出できました。
ただしこの結果は、一般的な目安とされる「6〜7分」を用いた値の一つにすぎません。大切なのは、自社の実績データをこの計算式に当てはめ、現実的な目標を設定することです。
☝️一言アドバイス!
AHTの目標設定は、業界平均を参考にしつつも、自社のサービス内容や顧客層に合わせて調整することが重要です。目標達成を急ぐあまり、オペレーターに過度なプレッシャーを与えないよう注意しましょう。
コールセンターのAHTが長くなる5つの原因
この章の要約!
AHTが長引く主な原因は、オペレーターのスキル不足や非効率な業務プロセスにあります。原因を正しく特定することが、効果的なAHT改善の第一歩です。
AHTの改善に取り組む前に、なぜ時間がかかっているのか、その根本的な原因を突き止める必要があります。原因は一つとは限らず、複数の要因が複雑に絡み合っていることも少なくありません。
ここでは、5つの原因に分けて詳しく解説します。
原因1:オペレーターの知識・スキル不足
商品やサービスに関する知識が不足していると、回答を探すのに時間がかかります。
また、システムの操作に不慣れなことも、処理時間を長引かせる一因です。特に新人オペレーターに多く見られます。
原因2:保留時間の多発
上司であるスーパーバイザーへの判断依頼や対応の引き継ぎ(エスカレーション)、関連部署への問い合わせが頻繁に発生すると、その分、保留時間が長くなります。
これは、オペレーター個人では解決できない情報不足や権限の制約が背景にある可能性があります。
原因3:後処理時間(ACW)の長さ
通話後の応対履歴の入力に時間がかかっているパターンです。
入力すべき項目が多すぎたり、記載ルールが複雑だったりすると、オペレーターの負担が増え、ACWが伸びる傾向にあります。
原因4:トークスクリプトやFAQに問題がある
トークスクリプトが分かりにくかったり、情報が古かったりすると、オペレーターはスムーズな案内ができません。
また、社内FAQの検索が使いにくいと、必要な情報をすぐに見つけられず、顧客を待たせてしまうことがあります。
原因5:コミュニケーションの問題
顧客が本当に聞きたいことを正確に引き出せないと、会話が堂々巡りになりがちです。
また、問題解決に直接関係のない雑談が長引くことも、AHTを伸長させる要因の一つになるでしょう。
明日から実践できる!AHTを短縮する7つの方法
この章の要約!
AHT改善は「オペレーター教育」「業務プロセスの見直し」「ツールの活用」という3つの軸で進めます。一つずつ着実に実践することで、応対品質を維持しながらAHTを短縮できます。
AHTが長くなる原因を特定したら、次はいよいよ改善策の実行です。以下の3つの軸から、7つの方法に取り組みましょう。
【オペレーター教育】
- 応対品質基準の明確化と研修の実施
- ナレッジマネジメントの強化
【業務プロセス改善】
- トークスクリプトの最適化
- FAQ・マニュアルの整備
- 後処理(ACW)の効率化
【ツール活用】
- CTIシステムの導入・見直し
- 通話分析ツールの活用
それぞれ詳しく解説します。
1.応対品質基準の明確化と研修の実施
良い応対とは何か、具体的な基準を定義し、オペレーター全員で共有することが重要です。
テキストだけでなく、模範となる応対の録音データを活用した研修や、定期的なロールプレイングを実施することで、チーム全体の応対スキルを底上げし、標準化を図ることができます。
2.ナレッジマネジメントの強化
個人のスキルに依存するのではなく、組織全体の知識として優れた応対ノウハウを蓄積・共有する仕組みを構築しましょう。
ベテランオペレーターの応対を文字起こししてナレッジ化したり、システムの操作研修を徹底したりすることで、新人でも早い段階で質の高い対応が可能になります。
3.トークスクリプトの最適化
顧客の質問の流れを予測し、分岐を分かりやすく整理したフローチャート形式のスクリプトを導入すると、オペレーターは瞬時に適切な案内を選択できます。
また、ウェブサイトのFAQページへ誘導するなど、顧客の自己解決を促す案内を組み込むことも、入電数削減につながります。
4.FAQ・マニュアルの整備
オペレーターが必要な情報に少しでも早くたどり着けるよう、FAQやマニュアルを探しやすくする工夫が欠かせません。キーワード検索の精度を向上させたり、カテゴリ分類を見直したりして改善しましょう。
また、情報が常に最新の状態に保たれるよう、定期的な更新フローを確立することも大切です。
5 後処理(ACW)の効率化
後処理時間は、工夫次第で大きく削減できる領域です。応対履歴の入力項目を必要最小限に絞り込んだり、定型文を登録できるテンプレート機能を活用したりすることが有効です。
さらに、AIによる通話の自動要約ツールを導入すれば、オペレーターの作業負荷を大幅に軽減できます。
6 CTIシステムの導入・見直し
CTIシステムを活用し、電話着信と同時に顧客情報や過去の応対履歴をPC画面に表示(ポップアップ)させることで、オペレーターは顧客の名前や状況をすぐに把握できます。
毎回情報をヒアリングする手間が省け、スムーズに本題に入れるため、通話時間の短縮を促進します。
7.通話分析ツールの活用
AIを搭載した通話分析ツールは、AHT改善の強力な武器となります。全ての通話を自動で文字起こしし、保留や沈黙が長い箇所、顧客と会話が被っている箇所などを可視化します。
客観的なデータに基づいて課題点を特定できるため、効果的な改善策を効率的に立案できます。
☝️一言アドバイス!
AHT改善は、オペレーター個人の努力だけに頼るのではなく、チーム全体で取り組むことが成功の鍵です。特に、FAQやマニュアルの充実は、新人オペレーターの即戦力化にもつながり、チームの底上げに貢献します。
AHTの改善と顧客満足度の向上を両立させるコツ
この章の要約!
AHTの短縮だけを追求すると、顧客満足度の低下やオペレーターの疲弊を招く危険があります。AHTはあくまで「結果」と捉え、応対品質の向上を目指すことが重要です。
AHTの改善は多くのコールセンターの課題ですが、その過程で応対品質を犠牲にしては本末転倒です。
以下に、AHTの改善と顧客満足度の向上を両立させるためのコツを整理しました。
AHTの改善は多くのコールセンターの課題ですが、その過程で応対品質を犠牲にしては本末転倒です。
以下に、AHTの改善と顧客満足度の向上を両立させるためのコツを整理しました。
◎避けるべき運用方法(応対品質の低下)
| 項目 | 起こりうる問題・リスク |
|---|---|
| AHT数値の絶対視 | 時間内に終えることが目的化し、早口で機械的な応対になりがち。顧客に不快感を与え、企業の評判を損ねる恐れがある。 |
| AHTのみでの人事評価 | オペレーターが常に時間に追われ、丁寧なヒアリングや提案が困難になる。結果として根本解決に至らず、再入電を招く。 |
| 無理な時間短縮の強要 | オペレーターが委縮し、必要な確認や情報提供を怠る原因となる。 |
◎推奨される運用方法(応対品質の向上)
| 項目 | 期待される効果 |
|---|---|
| 品質とセットでの目標管理 | 顧客満足度アンケートなどとセットで目標管理することで、応対の質と効率のバランスを取る意識が生まれる。 |
| プロセス評価の導入 | オペレーターの前向きなスキルアップ意欲を促進し、長期的な品質向上に繋がる。 |
| ツール活用による無駄の削減 | オペレーターが顧客との対話そのものに集中できる時間を創出し、応対の質を高める。 |
このように、AHTを単なる数字として追うのではなく、応対品質向上の結果として捉える視点の転換が、本質的な改善に欠かせないのです。
【業界・目的別】優先すべきAHT改善のポイント
この章の要約!
AHT改善のアプローチは、インバウンドかアウトバウンドか、またテクニカルサポートか受注窓口かによって異なります。自社の目的に合った最適な改善策を見つけることが、成功への近道です。
全てのコールセンターに通用する万能なAHT改善策はなく、自社のセンターが担っている役割によって変わります。
ここでは、インバウンド、アウトバウンド、テクニカルサポート、受注・問い合わせ窓口の4ケースに分けて、優先すべきAHTの改善ポイントをお伝えします。
インバウンド(受信)コールセンターのケース
目的: 問題解決と顧客満足度向上
ポイント: FAQを充実させて顧客の自己解決を促し、入電を減らすことが有効です。また、一度の電話で問題を解決する初回コンタクト解決率(FCR)を高めることで、結果的にAHTの適正化と満足度向上に繋がります。
アウトバウンド(発信)コールセンターのケース
目的: アポイント獲得や契約締結
ポイント: AHTの長さ自体よりも、会話の質や目的の達成率が重視されます。AHTを意識しすぎて拙速な案内になるのは避けるべきです。成果を上げているオペレーターのトークを分析し、そのノウハウを共有することが有効です。
テクニカルサポートのケース
目的: 複雑な技術的問題の解決
ポイント: 複雑な内容を扱うため、AHTは必然的に長くなる傾向にあります。無理な短縮は目指さず、正確な情報を伝え、段階的に問題を切り分けるロジカルな対話スキルを磨くことが、顧客満足度の向上に繋がります。
ECサイトの受注・問い合わせ窓口のケース
目的: 迅速な注文処理と機会損失の防止
ポイント: スピーディーな対応が求められるため、システム操作の習熟度向上がAHT短縮に直結します。入力ミスを減らす仕組み作りも重要です。余裕が生まれた時間で、関連商品をおすすめするアップセルなども可能になります。
AHTに関するよくある質問
AHTに関して、多くのコールセンター管理者様から寄せられる質問とその回答をまとめました。皆様の疑問解決の一助となれば幸いです。
Q1.AHTの目標値は、どのくらいに設定すれば良いですか?
A. 業界や問い合わせ内容によって大きく異なりますが、一般的には6分前後を目標とするケースが多いです。
まずは自社の現状のAHTを正確に把握し、そこから10%削減、15%削減といった段階的な目標を設定することをおすすめします。業界平均はあくまで参考値として捉えましょう。
Q2.AHTは短ければ短いほど良いのでしょうか?
A. いいえ、一概にそうとは言えません。無理なAHT短縮は、顧客に必要な情報を提供しきれなかったり、冷たい印象を与えたりするリスクがあり、かえって顧客満足度の低下を招くことがあります。
応対品質を維持、向上させた結果としてAHTが短縮されるのが理想的な状態です。
Q3.AHT短縮と顧客満足度は、どうすれば両立できますか?
A. オペレーター個人の努力に頼るのではなく、FAQシステムの整備や、後処理を自動化するツールの導入など、仕組みで解決することが重要です。また、AHTと合わせて顧客満足度アンケートの数値もKPIとして追うことで、応対品質の低下を防ぎながら改善を進めることができます。
Q4.後処理時間(ACW)が長いのですが、どうすれば短縮できますか?
A. 応対履歴の入力テンプレートを作成したり、よく使う文言を単語登録したりするのが効果的です。また、通話内容をAIが自動で要約してくれるツールを導入すれば、オペレーターは内容の確認・修正だけで済むため、後処理時間を大幅に削減できます。
Q5.SV(スーパーバイザー)として、AHT改善のために何をすべきですか?
A. 個々のオペレーターのAHTをただ指摘するのではなく、AHTが長い通話の録音を聞き、具体的な原因(保留が多い、説明が冗長など)を一緒に分析し、改善に向けたコーチングを行うことが重要です。また、FAQの更新や研修の企画など、チーム全体のパフォーマンスを底上げする環境作りに努めましょう。
まとめ:効率的なAHT改善なら電話解析AI「MiiTel Phone(ミーテルフォン)」

この記事では、AHTの基本的な知識から原因分析、具体的な改善策まで詳細に解説しました。
AHTの改善は、応対品質とのバランスを取りながら、原因を特定し、多角的な施策を地道に続ける必要があり、決して簡単ではありません。
これらの課題をテクノロジーで解決し、効率的なAHT改善と応対品質向上を両立するのが、電話解析AI「MiiTel Phone(ミーテルフォン)」です。
全通話の自動録音と文字起こし機能
SVが全ての応対を客観的に振り返り、的確なフィードバックが可能に。保留や沈黙の長い通話を抽出し、原因分析の時間を大幅に短縮します。
AIによるトーク分析・評価
話速、被り、ラリー数などをAIが自動でスコアリング。オペレーター自身が応対を客観的に振り返り、セルフコーチングでスキルアップできます。
優れた応対内容の横展開
トップセールスや顧客満足度の高いオペレーターの応対を「お手本」として全社で共有。組織全体の応対品質を底上げし、結果としてAHTの適正化につながります。
応対内容の自動要約機能
AIが通話内容を自動で要約。オペレーターは後処理(ACW)でゼロから文章を作成する必要がなくなり、入力時間を削減できます。
MiiTel Phoneは、AHT改善はもちろん、コールセンターが抱える売上向上やオペレーター教育など、幅広い課題解決にも貢献します。
まずは資料で機能や活用方法をご確認いただき、AHT改善の具体的なイメージをつかんでみてください。