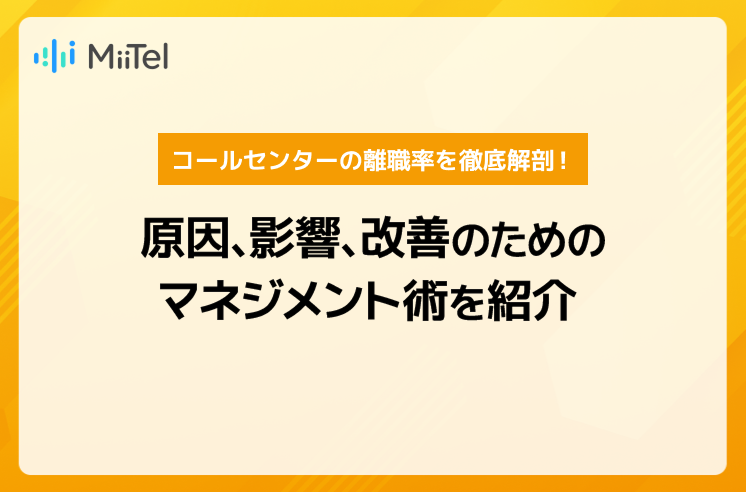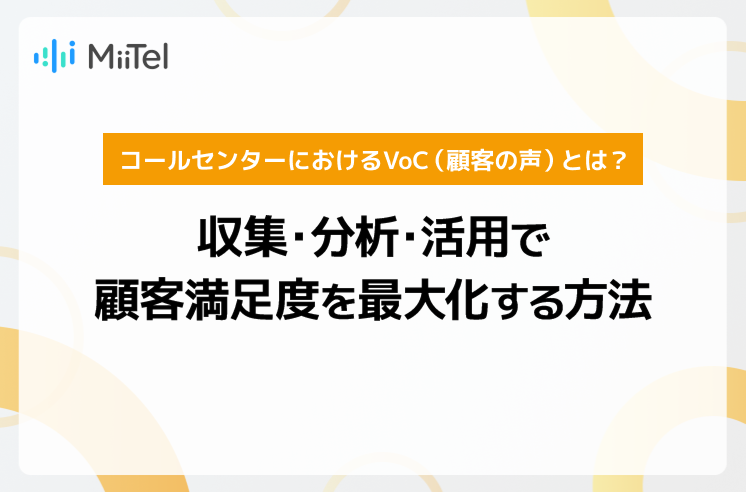コールセンターモニタリング実践ガイド:応対品質向上とオペレーター育成を加速する方法
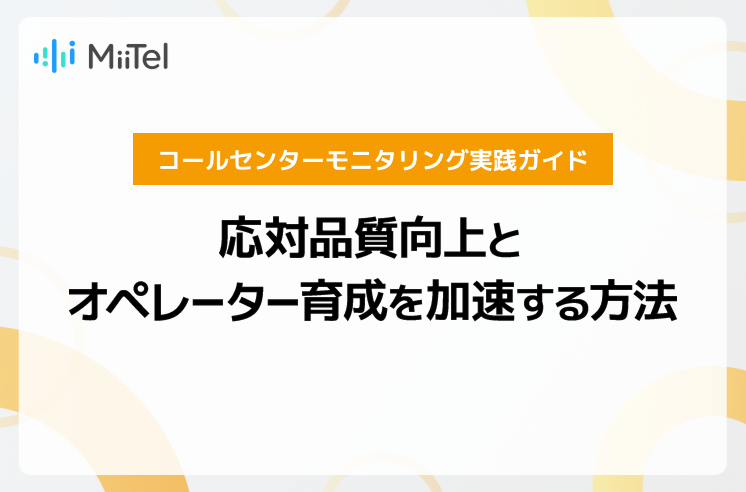
インサイドセールス・電話営業の業績向上なら電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」
インサイドセールス・電話営業の業績向上なら
電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」
目次
コールセンター運営において、「応対品質のばらつき」「新人オペレーターの育成」「顧客満足度の向上」といった課題は尽きません。これらの課題に正面から向き合い、センター全体のパフォーマンスを継続的に向上させるための鍵となるのが「モニタリング」活動です。
しかし、多くの現場で「重要性は理解しているけれど、具体的な進め方が分からない…」「形骸化してしまっている」という声が聞かれます。
この記事は、コールセンターの品質管理とコールセンター業務の支援をしてきた経験に基づき 、モニタリングを単なるチェック作業で終わらせず、確実に成果へと繋げるための実践的な方法論を体系的に解説します。
モニタリングの基本から、具体的なステップ、効果を最大化するフィードバック術、最新のツール・AI活用、そして陥りがちな失敗とその対策まで、貴社のコールセンターを次のステージへ引き上げるための具体的なノウハウをお伝えします。
すぐに現場で活用できるモニタリングシートの雛形も掲載しますので、ぜひ最後までお読みいただき、明日からの改善活動にお役立てください。
コールセンターモニタリングの基本:目的と種類
効果的なモニタリング計画の第一歩は、その基本である「目的」と「種類」を正しく理解することから始まります。
モニタリングとは?目的を明確にする
コールセンターにおけるモニタリングとは、オペレーターの顧客対応(主に通話)を客観的に評価・分析し、応対品質の維持・向上、オペレーターの育成、そしてセンター全体のパフォーマンス向上を目的とした、戦略的なマネジメント活動です。決して「監視」や「粗探し」が目的ではありません。
モニタリングを通じて達成すべき主な目的は、以下の通りです。これらを自社の状況に合わせて具体化し、関係者間で共有することが成功の第一歩となります。
- 応対品質の維持・向上と標準化: センターとして目指すべき品質レベルを定義し、それを全員が満たせるよう、現状のレベルを測定し、課題を特定・改善します。これにより、顧客体験の均質化を図ります。
- オペレーターのスキルアップ・育成支援: 各オペレーターの強み・弱みを客観的なデータに基づいて把握し、的確なフィードバックと育成計画を提供します。OJTの中核として機能させることが重要です。
- 課題や問題点の早期発見と改善: 個々のオペレーターの問題だけでなく、トークスクリプト、業務プロセス、システムなど、センター全体が抱える構造的な課題を発見し、改善サイクルを回す起点とします。
- 顧客満足度(CS)の向上: 応対品質は顧客満足度に直結する重要な要素です。顧客の声に耳を傾け、期待を超える応対を目指すことで、ロイヤルティ向上に貢献します。
- コンプライアンス遵守の徹底: 法令や社内ルールが遵守されているかを確認し、潜在的なリスクを未然に防ぎます。これは企業の信頼を守る上で不可欠です。
- 成功事例の共有とナレッジ化: 優れた応対や効果的なトークを特定し、センター全体のナレッジとして蓄積・共有することで、組織全体のスキルアップを加速します。
まずは、これらの目的の中から、現在自社が最も注力すべきものは何かを明確に定義しましょう。
モニタリングの主な種類と特徴
モニタリングにはいくつかの手法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。目的に応じて最適な手法を選択し、組み合わせることが有効です。
【表:モニタリング種類別 比較】
| 種類 | 概要 | 主な目的 | メリット | デメリット |
| 事後モニタリング | 録音された通話を後から評価(最も一般的) | 品質評価、課題発見、育成、コンプライアンス | じっくり評価可能、客観性保ちやすい、複数評価可能 | 即時性がない、録音システムが必要 |
| リアルタイムモニタリング | 通話中にSVなどが応対を聞き、支援する | 新人支援、即時介入、トラブル防止 | 問題発生時にすぐ対応可能、即時フィードバック可能 | SVの負担が大きい、オペレーターにプレッシャー |
| セルフモニタリング | オペレーター自身が応対を振り返る | 自己認識促進、主体的な改善意欲向上 | オペレーターの気づき促進、納得感を得やすい | 客観性に欠ける可能性、基準理解が必要 |
| ピアモニタリング | オペレーター同士が相互評価 | 相互学習、チーム内での基準共有、多様な視点 | 気軽に実施しやすい、オペレーター間の学び促進 | 関係性への配慮が必要、評価のばらつきが出やすい |
| サイレントモニタリング | オペレーターに告知せずに応対を聞く | 日常の自然な応対把握、不正検知 | 普段通りの応対を確認可能 | オペレーターの不信感に繋がるリスク |
多くのセンターでは、客観的な品質評価のために事後モニタリングを主軸としつつ、新人育成のためにリアルタイムモニタリングを、オペレーターの主体性向上のためにセルフモニタリングやピアモニタリングを補助的に組み合わせるケースが見られます。自社のリソースと目的に最適な組み合わせを検討しましょう。
実践!効果的なコールセンターモニタリングの進め方(5ステップ)
モニタリングを成果につなげるためには、体系立てられたプロセスに沿って進めることが重要です。ここでは、多くの現場で有効性が確認されている5つのステップをご紹介します。

ステップ1:モニタリングの目的と目標を具体的に設定する
モニタリング活動の成否は、この最初のステップ、「目的と目標の明確化」で大きく左右されます。 なぜモニタリングを行うのか、それによって具体的にどのような状態を目指すのかを定義し、関係者全員で共有することが不可欠です。
- 目的の明確化: まず、自社の課題(例:クレームが多い、成約率が低い、AHTが長い)を特定し、それを解決するためにモニタリングで何を目指すのか(例:応対品質の標準化、特定スキルの強化)を言語化します。
- 具体的な目標設定: 目的を達成するための具体的な指標(KPI)と目標値を設定します。「〇ヶ月後にクレーム件数を〇%削減」「新人オペレーターの保留時間を平均〇秒短縮」のように、SMART原則を意識して設定しましょう。
- Specific(具体的)
- Measurable(測定可能)
- Achievable(達成可能)
- Relevant(関連性)
- Time-bound(期限)
- 関係者間の合意形成: 設定した目的と目標は、マネジメント層、SV、そしてオペレーターにも(目標達成の意義として)共有し、活動への理解と協力を得ることが重要です。
「なんとなくモニタリングする」のではなく、この目的・目標設定にしっかり時間をかけ、活動の羅針盤とすることが成功への第一歩です。
ステップ2:評価項目と評価基準を策定する
モニタリングの客観性、公平性、そして育成効果を担保する上で、最も重要なのが「評価項目」と「評価基準」の策定です。 ここが曖昧だと、評価は評価者の主観に左右され、オペレーターの納得感も得られません。
- 評価項目の選定: ステップ1で設定した目的に直結する項目を選びます。「顧客満足度向上」なら共感力や問題解決力、「効率化」なら処理の正確性や迅速性など、重視すべきスキルや行動を具体的にリストアップします。一般的なカテゴリ例は以下の通りです。
【チェックリスト/テーブル:評価項目例リスト】
カテゴリ 評価項目例 ① 基本応対スキル ・第一声(名乗り、挨拶)・言葉遣い(丁寧語、尊敬語、謙譲語)・声のトーン、スピード、明瞭さ・相槌、クッション言葉・復唱確認・クロージング(お礼、締めの挨拶) ② コミュニケーションスキル ・傾聴力(相手の話を最後まで聞く姿勢)・共感力(相手の気持ちに寄り添う姿勢)・質問力(状況やニーズを的確に引き出す)・説明力(専門用語を避け、分かりやすく伝える) ③ 業務知識・処理スキル ・商品・サービス知識の正確性・業務プロセスの理解度・システム操作の正確性・迅速性・FAQやマニュアルの適切な活用・保留時間の適切さ ④ 問題解決能力 ・顧客の状況・真意の把握力・問題点の特定力・解決策の適切な提案力・代替案の提示・エスカレーション判断の適切さ ⑤ コンプライアンス遵守 ・個人情報の取り扱いルール遵守・関連法規(特商法など)の遵守・禁止用語・表現の不使用・社内ルールの遵守(報告手順など) ※自社のサービス特性や強化したいスキルに合わせて、これらの項目を精査・カスタマイズしてください。
- 評価基準の具体化: 各評価項目について、「何を」「どのレベルで」できたら何点(あるいはどの評価)とするのか、誰が評価しても同じ解釈ができるように具体的に定義します。
- 評価尺度の設定: 3~5段階評価やYes/Noなど、評価しやすい尺度を選びます。
- 各段階の定義: 「良い」「普通」「悪い」といった抽象的な言葉ではなく、「常に正しい敬語を使用し、丁寧で聞き取りやすい(5点)」「敬語の誤りが多く、顧客に不快感を与える可能性あり(1点)」のように、具体的な行動レベルで記述します。
- 定量評価(スコア)と定性評価(コメント)のバランス: 点数だけでなく、具体的な良かった点や改善点を記述するコメント欄を設け、フィードバックに厚みを持たせます。
- 評価者間の目線合わせ(キャリブレーション): 作成した基準に基づき、評価者全員で同じ応対を評価し、結果を比較・議論するキャリブレーション研修を定期的に実施します。これにより、評価のブレを最小限に抑え、公平性を担保します。これは手間がかかりますが、モニタリングの信頼性を維持するために不可欠なプロセスです。
「具体的で客観的な評価基準」と「評価者間の目線統一」、この二つが揃って初めて、モニタリングは有効なツールとなり得ます。
ステップ3:モニタリング対象者と実施頻度を決定する
誰の応対を、どのくらいの頻度でモニタリングするのかは、目的とリソース(評価者の工数など)を考慮して決定します。
- 対象者の考え方: 新人には早期育成のため高頻度に、課題を持つオペレーターには集中的に、全オペレーターには品質維持のため定期的に(例:月1~2回)実施するなど、目的に応じたメリハリが必要です。ベテランも例外ではありません。
- 頻度の考え方: 多すぎると評価者の負担が増し、少なすぎると効果測定やタイムリーな介入が難しくなります。多くのセンターでは月1~4回/人程度が目安ですが、自社の状況に合わせて最適なバランスを見つけましょう。
- 対象通話の選定: ランダム抽出を基本としつつ、目的に応じて「長時間通話」「クレーム」「特定商品に関する問い合わせ」などを意図的に抽出することも有効です。
限られたリソースの中でモニタリング効果を最大化するため、対象と頻度の戦略的な設計が求められます。
ステップ4:モニタリングを実施する際の注意点
実際のモニタリング実施においては、客観性と公平性を保ち、オペレーターとの良好な関係を維持するために、以下の点に留意しましょう。
- 評価基準の遵守と客観性の維持: 評価は必ず事前に定めた基準に基づいて行い、個人的な感情や先入観を排除します。「頑張っているから」といった情実や、「前回も指摘したのに」といったバイアスは評価の信頼性を損ないます。あくまで事実に基づいた評価を心がけます。
- 目的と基準の事前周知と理解: なぜモニタリングを行うのか、どのような基準で評価されるのかを、事前にオペレーターへ丁寧に説明し、理解と納得を得ることが極めて重要です。「監視」ではなく「成長支援」のための活動であることを明確に伝え、ポジティブな動機づけを図ります。
- プライバシーへの配慮: モニタリング(特に録音)の実施については、オペレーター及び顧客に対して適切に告知するなど、個人情報保護の観点からもルールを明確にし、遵守を徹底します。
モニタリングは、評価者とオペレーターの信頼関係の上に成り立つ活動です。常に公平・公正な姿勢で臨むことが不可欠です。
ステップ5:モニタリングシートを作成・活用する
モニタリングの結果を正確に記録し、客観的な評価を担保し、効果的なフィードバックへと繋げるために、モニタリングシートの活用は必須です。
これは単なる記録用紙ではなく、育成のための重要なコミュニケーションツールとなります。
含めるべき主な項目は以下の通りです。
- 基本情報: 評価日、評価者、オペレーター名、対応日時、通話IDなど、評価対象を特定する情報。
- 評価項目・基準・評価点: 策定した評価項目と基準、および各項目の評価スコア。
- 良かった点(Good Point): 具体的な行動や発言レベルで、称賛すべき点を記述。成長を促す上で非常に重要。
- 改善点(Improvement Point): 具体的な行動や発言レベルで、改善が期待される点を記述。なぜ改善が必要か、どうすれば良くなるかのヒントも添える。
- 総合コメント: 全体的な所感や、特に伝えたいメッセージ、育成方針など。
- オペレーターコメント欄: フィードバックを受けたオペレーター自身が、気づきや感想、目標などを記入。自己認識と主体性を促す。
- 次回までのアクションプラン: フィードバックに基づき、オペレーターが取り組む具体的な行動目標。
このテンプレート案をベースに、自社の評価項目に合わせてカスタマイズし、ご活用してください。
このシートを効果的に活用することで、評価の客観性が高まり、フィードバックが具体的になり、オペレーターの成長プロセスを可視化することができます。
モニタリング効果を最大化する!効果的なフィードバックの方法
モニタリングは「評価して終わり」ではありません。その結果をオペレーターの成長に繋げる「フィードバック」こそが、モニタリング活動の核心です。 効果的なフィードバックは、オペレーターのスキルとモチベーションを高め、組織全体のパフォーマンスを向上させます。
なぜフィードバックが重要なのか?
質の高いフィードバックは、以下のような効果をもたらします。
- 自己認識の深化: 自身の強みと弱みを客観的に把握する機会を提供します。
- 具体的な行動変容の促進: 「何を」「どのように」改善すれば良いかが明確になり、行動に移しやすくなります。
- モチベーションの向上: 認められる経験(承認)と、成長できる実感(期待)が、仕事への意欲を高めます。
- 信頼関係の構築: 率直な対話を通じて、上司(SV)とオペレーター間の相互理解と信頼関係が深まります。
フィードバックは、オペレーター育成の根幹であり、エンゲージメント向上の鍵となる重要なコミュニケーションです。
オペレーターの成長を促すフィードバックの9つのポイント
効果的なフィードバックを実現するための、実践的な9つのポイントをご紹介します。これらを意識するだけで、フィードバックの質は格段に向上します。
- 即時対応 : モニタリング後、できるだけ早く(当日~翌日推奨)実施し、記憶が新しいうちに振り返る機会を作る。
- 具体性 : 「良かった」「悪かった」ではなく、「〇〇という表現がお客様の状況を的確に捉えていました」「△△の案内が少し早口だったので、もう少しゆっくり話すと伝わりやすいです」のように、具体的な行動・発言を引用する。
- 客観評価 : 評価者の主観ではなく、モニタリングシートと評価基準に基づき、事実を伝える。
- ポジティブファースト : まず良かった点を具体的に認め、自信を育む。その上で改善点を伝え、最後に期待を述べる(サンドイッチ法など)。承認はモチベーションの源泉です。
- 対話を重視: 一方的に話さず、「どう思いますか?」「どうすれば良かったと考えますか?」と問いかけ、オペレーター自身の考えや気づきを引き出す。傾聴の姿勢が重要。
- 改善点は絞る: 一度に多くの課題を指摘せず、最も重要な改善点1~2つに絞り、着実なステップアップを促す。
- 人格でなく行動に注目 : 人格を否定するような言葉は厳禁。「今回の応対におけるこの行動」というように、事実に焦点を当てる。
- 行動計画づくりを支援 : 「次回はどう改善するか」をオペレーター主体で考えさせ、具体的なアクションプランを共に設定する。自己決定感が成長を促す。
- 継続フォロー: フィードバックで決めたアクションプランの実践状況を、その後のモニタリングや日々の関わりの中で継続的に確認し、サポートする。小さな進歩も認め、励ます。
これらのポイントを実践し、フィードバックを「評価の場」から「共育(共に育つ)の場」へと変えていきましょう。
★フィードバック面談の具体的な進め方
実際のフィードバック面談を効果的に進めるためのポイントです。
- 事前準備: モニタリングシートを読み込み、伝えるべき「良かった点」「改善点」「具体的な行動例」を整理しておく。
- 場所の確保: 周囲を気にせず話せる、静かでプライバシーの保たれた空間を用意する。
- 面談の流れ(例): ①アイスブレイク → ②目的説明 → ③良かった点の承認 → ④改善点の伝達(事実と理由) → ⑤オペレーターの意見傾聴 → ⑥行動計画の共創 → ⑦まとめと励まし。
- 時間配分: 事前に目安時間を設定し、特にオペレーターが話す時間、行動計画を考える時間をしっかり確保する。
評価者(SV)の傾聴力と質問力が、面談の成否を分けます。
コールセンターモニタリングの効率化と高度化:ツールとAIの活用
モニタリング業務の効率化と分析能力の向上は、多くのセンターにとって重要な課題です。ここでは、テクノロジー活用の現状と可能性について解説します。
モニタリングを支援するツール・システムの種類と選び方
モニタリング業務を効率化し、質を高めるための代表的なツールです。
- 通話録音システム: 全てのモニタリングの基礎。検索・再生機能が重要。
- 音声認識システム(テキスト化): 通話をテキスト化。内容確認の効率化、キーワード検索、分析基盤として活用。認識精度が選定ポイント。
- テキストマイニングツール: テキストデータからVOC(顧客の声)の傾向、頻出語、関連語などを分析。課題発見やFAQ改善に活用。
- 感情分析ツール: 声のトーンなどから感情を推定。CS/ES分析の補助やクレーム予兆検知などに活用されるが、精度には限界も。
- 応対品質管理システム: モニタリング評価、フィードバック管理、集計・分析レポート作成などを一元管理。業務全体の効率化に貢献。
ツール選定時のポイントは、「導入目的の明確化」「費用対効果」「必要な機能と操作性」「サポート体制」「既存システム連携」です。「ツール導入ありき」ではなく、自社の課題解決に本当に役立つかを慎重に見極めましょう。デモやトライアルの活用が有効です。
実際に、多くの企業で導入が進む「MiiTel Phone(ミーテルフォン)」は、自動録音・自動全文文字起こし・通話中のモニタリング・トーク解析などで、業務を効率化・高度化を実現しています。
また、Salesforce・kintone・Huspot などのCRM・SFAと自動連携が可能です。
導入事例や詳細な機能については、以下のページからご覧いただけます。
AI活用でモニタリングはどう変わる?可能性と導入のポイント
AI技術はモニタリングのあり方を大きく変えつつあります。その可能性と注意点を理解しておくことが重要です。
- AIによるモニタリングの可能性:
- 評価の自動化(一部): 定型的なルール(必須案内、NGワード等)に基づく評価を自動化し、評価工数を大幅に削減できる可能性がある。
- 全量モニタリングへの道: 人手では不可能だった全通話のチェックに近づき、リスクや改善機会の見逃しを減らす。
- 高度な分析とインサイト発見: 大量データから人間では気づかない傾向、課題、顧客ニーズを抽出し、サービス改善や戦略立案に貢献。
- コンプライアンスチェックの強化: 不正やルール違反の兆候を自動検知。
- AI導入・活用の注意点:
- 定性評価の限界: 共感力、表現のニュアンスといった人間の感覚が必要な評価はAIには難しいのが現状。
- 精度とチューニング: 音声認識精度やAIの評価ロジックは完璧ではなく、自社業務に合わせた**継続的なチューニング(教育)**が必要。
- 人間の役割の重要性: AIはあくまで強力な「支援ツール」。最終的な判断、オペレーターへの心のこもったフィードバックや育成は、依然として人間の重要な役割。
- 目的の明確化とスモールスタート: 何のためにAIを使うのかを明確にし、まずは限定的な範囲で導入・効果検証を行うことが推奨される。
AIの進化は目覚ましいですが、過度な期待は禁物です。AIと人間がそれぞれの強みを活かし、協働することで、モニタリングの価値を最大化できるでしょう。
電話解析AI「MiiTel Phone(ミーテルフォン)」は、AIにより通話内容を可視化・解析する機能を備えたIP電話サービスです。トーク比率や話速、ラリー回数などを解析し、ハイパフォーマーの会話傾向を見える化し把握できます。
さらに、生成AIオプション※を利用することで、会話内容に基づいたアドバイスを表示する会話コーチング機能も活用できます。
コールセンター向けオプション「MiiTel Call Center」と組み合わせることで、より多角的なモニタリングにも対応可能です。
※ 会話コーチングなど一部機能のご利用にはオプション契約が必要です。
失敗しない!コールセンターモニタリング導入・運用の注意点
最後に、モニタリングを確実に成功させるために、陥りやすい失敗とその対策、そして継続的な改善とコンプライアンスの重要性について確認します。
コールセンターモニタリングでよくある失敗例とその対策
多くの現場で見られるモニタリングの失敗パターンです。自社の状況と照らし合わせ、対策を講じましょう。
- 失敗例①:目的が曖昧なまま形骸化
- 状況: 何のためにやっているか不明確なまま、ただ評価シートを埋める作業になっている。
- 対策: → 常に「目的・目標」に立ち返る。モニタリング結果がどう活用され、成果に繋がっているかを可視化する仕組みを作る。
- 失敗例②:評価基準が曖昧・不公平で納得感が低い
- 状況: 評価者による評価のバラつきが大きい。オペレーターは評価結果に不信感を抱く。
- 対策: → 具体的で客観的な基準定義と、定期的なキャリブレーションによる評価者間の目線合わせを徹底する。
- 失敗例③:フィードバックが一方的で育成につながらない
- 状況: スコア伝達のみ、またはダメ出し中心のフィードバックで、オペレーターが萎縮・反発する。
- 対策: → 「効果的なフィードバックの9つのポイント」を実践。承認と対話を重視し、成長支援の姿勢で臨む。
- 失敗例④:「監視」と捉えられモチベーション低下
- 状況: モニタリングの目的やポジティブな側面が伝わらず、オペレーターが管理強化と受け止める。
- 対策: → 「育成のため」であることを繰り返し伝え、成功体験や成長を共有する場を設けるなど、ポジティブな運用を心がける。
- 失敗例⑤:結果が分析・活用されず「やりっぱなし」
- 状況: 個別フィードバックで終わり、センター全体の課題特定や改善活動に繋がっていない。
- 対策: → モニタリングデータを定期的に集計・分析し、傾向や課題を特定。研修計画やマニュアル改善など、具体的なアクションに繋げるプロセスを確立する。
これらの失敗は、少しの意識と工夫で避けることができます。常に自社のモニタリング活動を客観的に見つめ直すことが重要です。
継続的な見直しと改善(PDCA)が不可欠
市場環境や顧客ニーズの変化に対応するため、モニタリング体制も定期的に見直し、改善していく必要があります。 一度作った評価基準や運用ルールが、常に最適とは限りません。
- PDCAサイクルの実践: Plan(計画・見直し)→ Do(実行)→ Check(効果測定・評価)→ Act(改善)のサイクルを意識的に回しましょう。
- 効果測定: モニタリングスコアの推移だけでなく、CS、NPS®、AHT、解決率、オペレーター満足度など、関連するKPIの変化を測定し、モニタリング活動の効果を多角的に評価します。
- 定期的なレビュー: 半年~年1回程度、モニタリングの目的、評価項目・基準、運用プロセス全体をレビューし、改善点がないか検討する機会を設けることを推奨します。
モニタリングは「生き物」です。常に最適な状態を目指し、改善し続ける姿勢が成功の鍵となります。
★コンプライアンスとプライバシーへの配慮
モニタリング実施においては、法令遵守と個人の権利保護が大前提です。
- 法令遵守: 個人情報保護法などの関連法規を正しく理解し、遵守した運用(録音の告知、データ管理方法など)を徹底します。
- オペレーターへの説明と同意: モニタリングの目的、方法、評価基準、データの取り扱いについて、事前に明確に説明し、理解と同意を得ておく(就業規則等への明記含む)ことがトラブル防止に繋がります。
- データの適切な管理: モニタリングで得た個人情報を含むデータは、アクセス権限設定、保管期間ルールなどを定め、厳重に管理します。
信頼なくして効果的なモニタリングはあり得ません。コンプライアンスとプライバシーへの配慮は、その信頼の基盤です。
まとめ
本記事では、コールセンターモニタリングを成功に導くための実践的な知識とノウハウを解説してきました。要点を振り返ります。
- モニタリングは品質向上・人材育成・CS向上に不可欠な戦略的活動。
- 成功の鍵は「明確な目的設定」「具体的・客観的な評価基準」「効果的なフィードバック」「継続的な改善(PDCA)」。
- ツールやAIは有効な支援手段だが、人間の役割(判断、フィードバック、育成)は依然として重要。
- コンプライアンスとプライバシーへの配慮は大前提。
モニタリングは、正しく設計・運用すれば、コールセンターのパフォーマンスを劇的に向上させるポテンシャルを秘めています。
ぜひ、この記事の内容と提供するテンプレートを参考に、まずは自社の「目的の再確認」や「評価基準の見直し」から始めてみてください。 そして、モニタリングを単なる業務ではなく、組織全体の成長エンジンとして機能させていきましょう。貴社のコールセンターが次のステージへと進化するための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
コールセンター業務の改善は「MiiTel Phone 」

電話解析AI「MiiTel Phone(ミーテルフォン)」 は営業トークにおける話速・会話の被せ率・沈黙回数などを定量的に分析・可視化することで、営業の生産性を向上してくれる電話解析AI です。電話・Web会議・対面での全ての会話のブラックボックス化の解消から会話データの利活用まで幅広くご利用いただけます。
具体的なメリット
- 通話内容の可視化: 話し方や言葉遣いを数値化し、客観的な評価が可能。
- 営業力強化: 成功事例を分析し、効果的な研修に繋げられます。
- 顧客満足度向上: 顧客の声を深く理解し、より良い対応に。
- 業務効率化: 文字起こしや要約機能で、情報検索がスムーズに。
こんな企業におすすめ
- 営業成績を向上させたい企業
- 顧客満足度を高めたい企業
- チーム全体のスキルアップを図りたい企業
- リモートワークの質を高めたい企業
MiiTel Phoneは、導入実績豊富なクラウド型のサービスです。
お気軽にご相談ください。